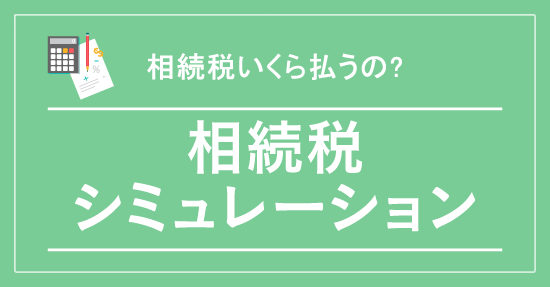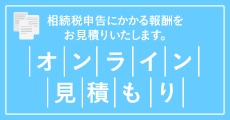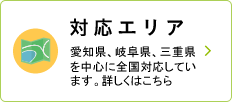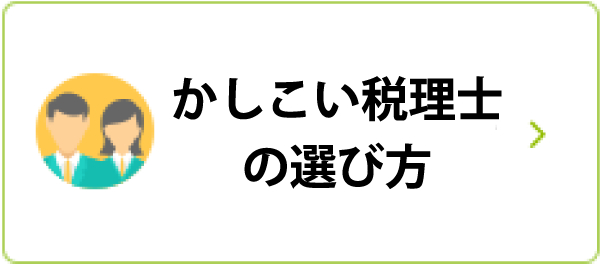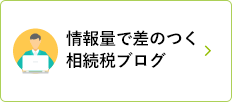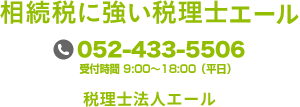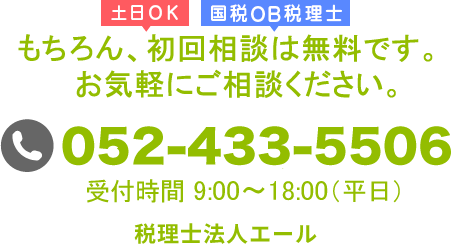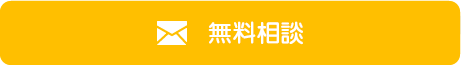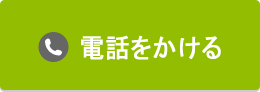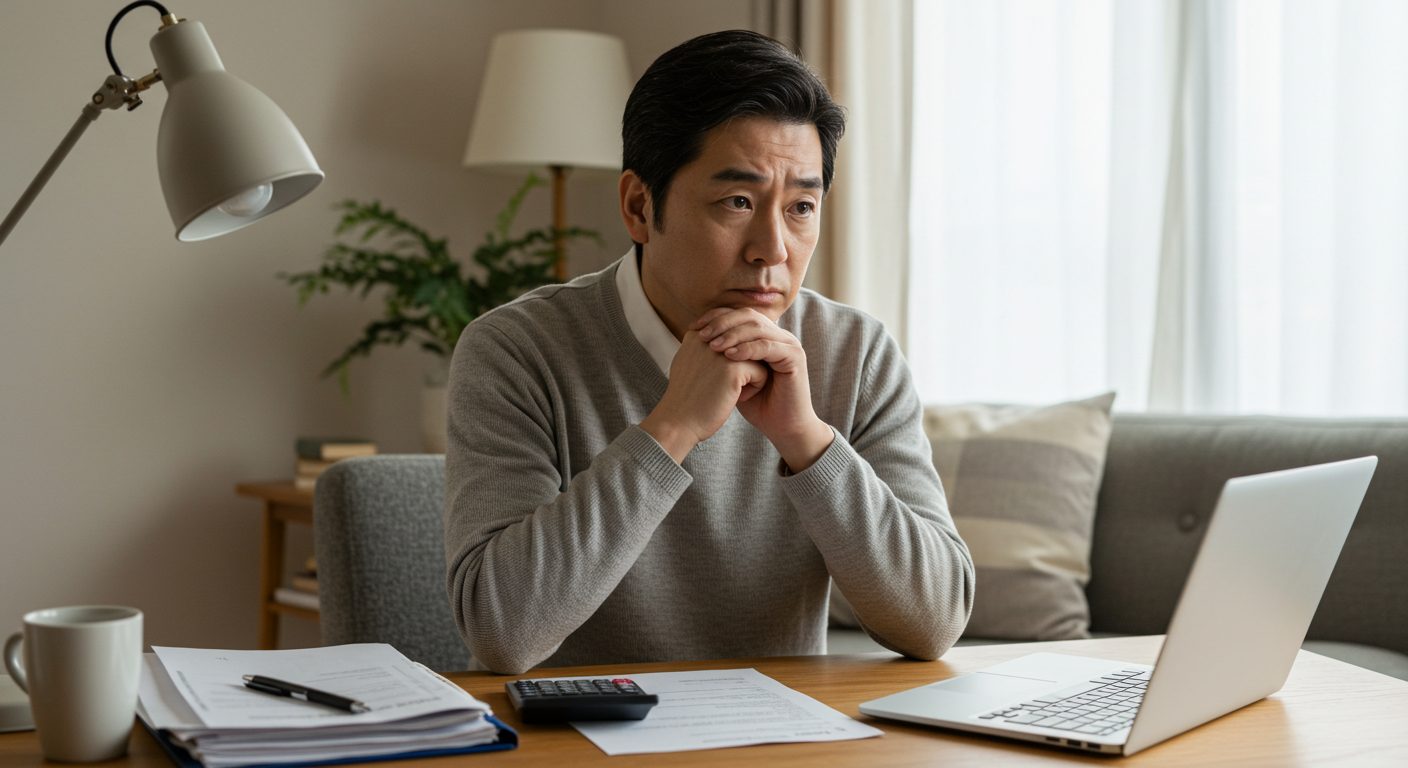
大切な家族を亡くし、悲しみに暮れる中で直面する相続手続き。「何から始めればいいのか分からない」「手続きを間違えたらどうしよう」そんな不安を抱えていませんか?
実は、相続税に強い税理士エールにご相談される方の80%が初めての相続を経験される方です。税理士と会うこと自体が初めてという方も少なくありません。
この記事では、初めて相続を経験する方が知っておくべき基本的なステップから、専門家に相談するタイミングまで、分かりやすく解説します。
目次
相続発生直後に確認すべき3つのポイント
遺言書の有無を最優先で確認
相続が発生したら、まず最初に行うべきは遺言書の有無の確認です。
「父が生前に『遺言書は書いていない』と言っていたから大丈夫」と思っていても、実際には書斎の引き出しや金庫の中から遺言書が見つかるケースは珍しくありません。
遺言書には主に3つの種類があります。
- 自筆証書遺言:被相続人が自分で書いた遺言書
- 公正証書遺言:公証役場で作成された遺言書
- 秘密証書遺言:内容を秘密にして公証役場で封印された遺言書
自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。これは遺言書の偽造や改ざんを防ぐための重要な手続きです。
一方、公正証書遺言の場合は検認手続きは不要ですが、公証役場で遺言書の有無を確認することができます。
相続人の正確な把握が争族回避の第一歩
次に重要なのが、相続人の確定です。「家族構成は分かっているから大丈夫」と思われるかもしれませんが、実はここに落とし穴があります。
例えば、お客様のAさん(50代男性)の事例をご紹介しましょう。Aさんの父親が亡くなり、相続人は母親、Aさん、弟の3人だと思っていました。ところが、父親の戸籍を調べてみると、若い頃に一度結婚歴があり、前妻との間に子供がいることが判明したのです。
この場合、その子供も法定相続人となるため、遺産分割協議には必ずその方の参加が必要になります。
相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等の収集が必要です。これは一般の方には複雑で時間のかかる作業ですが、正確に行わないと後々大きなトラブルの原因となります。
財産と債務の概算把握で全体像を掴む
相続人が確定したら、次は相続財産と債務の概算把握を行います。
ここでよくある誤解が「借金があるから相続放棄した方がいい」というものです。しかし、実際には借金があっても、それを上回る財産がある場合は相続した方が得になることも多いのです。
実際のお客様の事例では、父親に2000万円の借金があることが分かり、家族は相続放棄を検討していました。しかし、詳しく調べてみると土地や建物、生命保険金などの財産が4000万円あり、結果的に2000万円のプラスになることが判明しました。
このような判断を適切に行うためには、以下の財産を漏れなく把握する必要があります。
プラスの財産
- 現金・預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 株式・投資信託
- 生命保険金
- 退職金
- 貸付金
- その他の財産
マイナスの財産(債務)
- 借入金
- 住宅ローン
- 未払いの税金
- 医療費
- その他の債務
これらの概算把握は、相続放棄の判断だけでなく、相続税申告が必要かどうかの判断にも重要になります。
相続税申告が必要になるケースとは
基礎控除額を理解しよう
相続税は全ての相続に発生するわけではありません。相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合にのみ、相続税の申告と納税が必要になります。
基礎控除額の計算式は以下の通りです。 基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合: 3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円
この場合、相続財産の総額が4800万円を超えなければ、相続税の申告は不要です。
申告が必要でも税額がゼロになるケース
ただし、注意していただきたいのが「申告は必要だが税額はゼロ」になるケースです。
特に多いのが以下の特例を利用する場合です。
配偶者の税額軽減 配偶者が相続する財産が1億6000万円または法定相続分のいずれか大きい金額まで相続税がかからない制度
小規模宅地等の特例 自宅の土地や事業用の土地の評価額を大幅に減額できる制度
これらの特例を利用すれば税額がゼロになることもありますが、特例の適用を受けるためには必ず申告が必要です。申告を忘れると特例が適用されず、本来払わなくてよい税金を支払うことになってしまいます。
申告期限は相続開始から10カ月
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。
例えば、4月15日に相続が発生した場合、翌年の2月15日が申告期限となります。
この10カ月という期間は意外と短く、以下のような作業を行う必要があります。
- 戸籍等の収集
- 財産の調査・評価
- 遺産分割協議
- 申告書の作成
- 納税準備
特に不動産の評価や遺産分割協議に時間がかかることが多く、早めの準備が重要です。
税理士に依頼するメリットと選び方
自分で申告する場合のリスク
「相続税の申告は自分でもできるのでは?」と考える方もいらっしゃいますが、相続税申告には多くの専門知識が必要です。
実際に自分で申告された方の事例をご紹介します。Bさん(60代女性)は母親の相続で、財産の大部分が自宅の土地だったため「それほど複雑ではない」と考え、自分で申告を行いました。
しかし、申告後に税務調査が入り、土地の評価が適切でないとして追徴税額と加算税で200万円の追加負担が発生しました。最初から税理士に依頼していれば、適切な土地評価により税額を抑えることができ、結果的に費用を抑えることができたのです。
相続税に強い税理士の見分け方
税理士といっても、それぞれ得意分野が異なります。法人税や所得税は得意でも、相続税はあまり経験がないという税理士も少なくありません。
相続税に強い税理士を見分けるポイントは以下の通りです。
年間の相続税申告件数 年間50件以上の申告実績がある事務所が望ましいでしょう。
不動産評価の専門性 相続税では土地の評価が税額に大きく影響するため、不動産鑑定士との連携や豊富な評価実績があるかが重要です。
税務調査への対応力 元国税職員が在籍していたり、税務調査の対応実績が豊富な事務所は心強い味方になります。
料金の明確性 最初に料金体系を明確に提示し、追加料金の条件も説明してくれる事務所を選びましょう。
相続税に強い税理士エールの特徴
相続税に強い税理士エールでは、お客様の「残された遺産を1円も無駄にしたくない」という想いにお応えするため、以下のような特徴的なサービスを提供しています。
専門家チームによるサポート 税理士だけでなく、不動産鑑定士、元国税職員が連携してサポートします。これにより、多角的な視点から最適な申告を実現できます。
スピード対応 最短3週間での申告対応が可能です。期限が迫っているケースでも安心してお任せいただけます。
全国展開でのサポート 名古屋本店をはじめ、東京、横浜、大阪にも支店があり、全国のお客様にサービスを提供しています。
ワンストップサービス 相続登記や遺言書作成など、相続に関する手続きを一括でサポートします。複数の専門家を探す手間が省けます。
よくある疑問と解決策
「相続人同士の関係が悪化しそうで心配」
相続をきっかけに家族関係が悪化してしまう「争族」は珍しいことではありません。
実際のお客様の事例では、3人兄弟の相続で、長男が「自分が親の面倒を見てきたから多くもらって当然」と主張し、次男・三男が「法定相続分通りに分けるべき」と主張して話し合いが進まなくなりました。
このような場合、第三者である税理士が間に入ることで、法的根拠に基づいた客観的な提案を行うことができます。また、必要に応じて弁護士とも連携し、円満な解決を目指します。
「税務調査が来るのではないかと不安」
相続税の税務調査は約10%の確率で実施されると言われています。しかし、適切な申告を行っていれば過度に心配する必要はありません。
税務調査で問題になりやすいのは以下のようなケースです。
- 現金・預金の申告漏れ
- 名義預金(被相続人の財産を家族名義で管理していた預金)
- 不動産の評価額の相違
- 生前贈与の取り扱い
相続税に強い税理士エールでは、元国税職員の経験を活かし、税務調査で問題になりやすいポイントを事前にチェックし、根拠のある申告書を作成します。
「他の税理士に頼んでいるが相続だけ変更したい」
「普段の税務は今の税理士に満足しているが、相続だけは専門家に頼みたい」というご相談もよくいただきます。
このような場合でも全く問題ありません。相続税に強い税理士エールでは、相続申告のみのご依頼も承っています。
既存の税理士との関係を壊さないための上手な伝え方についてもアドバイスいたします。例えば「身内に相続専門の税理士がいるので」といった方法で、円満に専門家を活用することができます。
まとめ:安心の相続申告への第一歩
相続税申告は複雑で専門性の高い手続きですが、適切なステップを踏むことで確実に進めることができます。
重要なポイントをまとめると以下の通りです。
初期段階で行うべきこと
- 遺言書の有無確認
- 相続人の正確な把握
- 財産・債務の概算把握
専門家選びのポイント
- 相続税の実績が豊富
- 不動産評価に強い
- 税務調査対応力がある
- 料金体系が明確
相続税に強い税理士エールの強み
- 専門家チームによる多角的サポート
- 最短3週間のスピード対応
- 全国展開でのワンストップサービス
- 元国税職員による税務調査対策
初回のご相談は最大2時間まで無料で承っています。「何から始めればいいか分からない」という状況でも、現在の状況を詳しくお聞きし、具体的な進め方をご提案いたします。
相続は一生に何度も経験することではありません。だからこそ、専門家のサポートを受けながら、安心して手続きを進めることが大切です。
土日祝日も対応の直通電話(090-1294-4160)で、まずはお気軽にご相談ください。皆様の大切な財産を守るため、私たちが全力でサポートいたします。



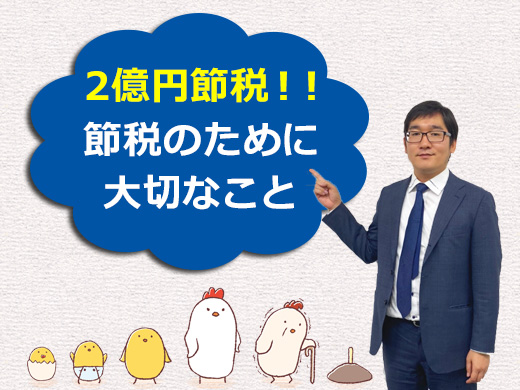

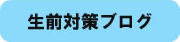
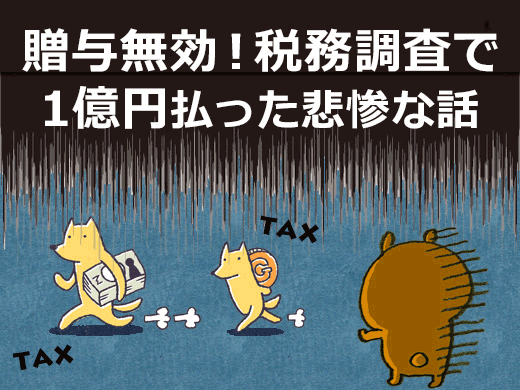

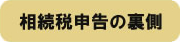


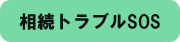
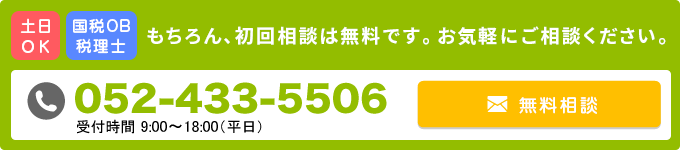
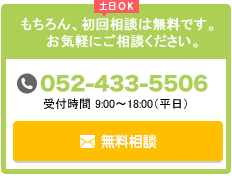

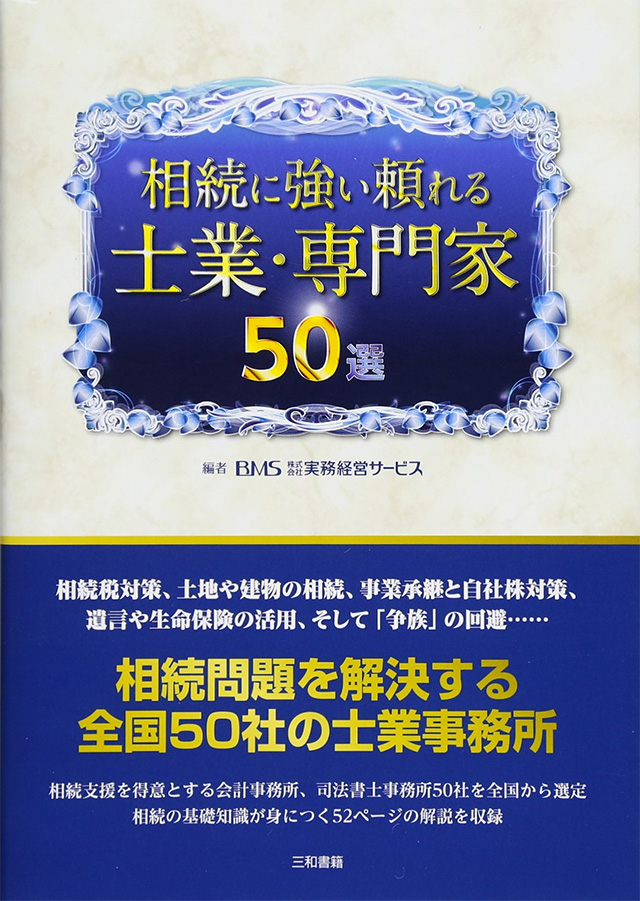
![ダイヤモンド・セレクト 2018年 12 月号 [雑誌]](https://nagae-sozoku.tax/cms/wp-content/themes/nagae-zeiri/img/asin_B07KH1S8NR.jpg)