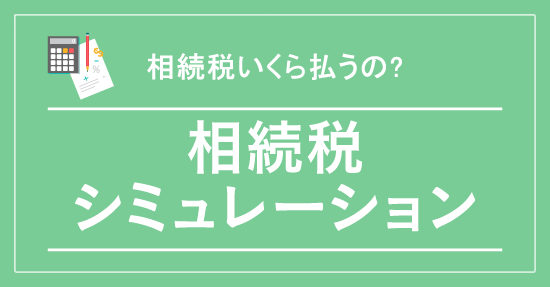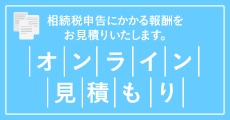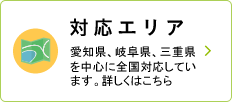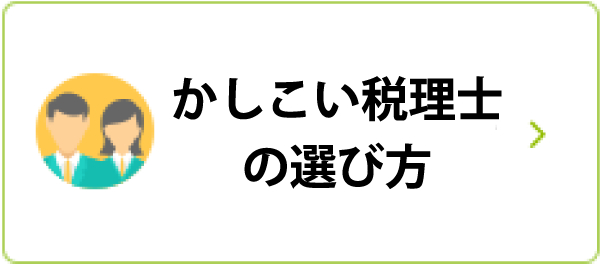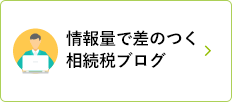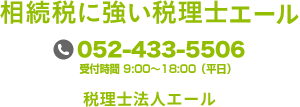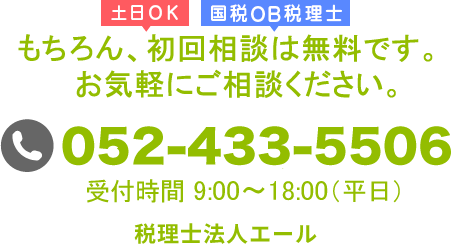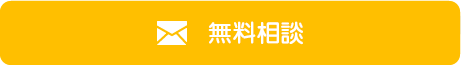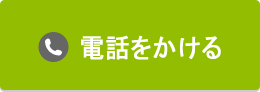「まさか、自分の生前贈与が認められないなんて…」。そう言って、税務調査後に巨額の追徴課税に直面する方は、残念ながら少なくありません。中には、「その贈与無効です!税務調査で1億円払った話」という衝撃的な事例があるように、良かれと思って行った生前対策が、かえって大きな負担となってしまうケースも存在します。
このブログを読んでいるあなたは、大切な資産を次世代に円満に引き継ぎたい、あるいは、すでに相続税の申告について税理士を探している最中かもしれません。ご自身に相続税が発生するかどうかも分からず、漠然とした不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、ご安心ください。ご相談に来られる方の80%が初めての相続を経験されており、分からないことだらけなのは当然のことです。税理士と会うこと自体が初めてという方も少なくありません。
目次
なぜ「贈与が無効」と判断されるのか?――税務調査の恐ろしさ
生前贈与は、相続税対策の非常に強力なツールであると同時に、そのやり方を間違えると、税務当局から「名義預金」とみなされ、贈与そのものが無効と判断されるリスクをはらんでいます。
税務調査では、財産が誰のものか、誰の意思で管理されているのかが厳しく問われます。形の上では贈与が行われたように見えても、実態が伴っていなければ、贈与は成立していないと判断されるのです。そして、生前贈与が無効と判断された場合、その財産は被相続人(贈与者)の相続財産として扱われ、多額の相続税が課税されることになります。
「その贈与、無効です!」と言われる典型的なパターン
税務調査において、贈与が無効と判断されやすい典型的なパターンをいくつか見ていきましょう。
1. 名義預金とみなされるケース
最も一般的なのが、親が子や孫の名義で口座を開設し、そこに資金を振り込んでいるものの、通帳や印鑑を親が管理し、子や孫がその預金の存在を知らない、あるいは自由に引き出せない場合です。
贈与が有効であるためには、贈与する意思(贈与者)と、贈与を受ける意思(受贈者)の両方があり、かつ受贈者がその財産を自由に使える状態になっていることが不可欠です。
2. 贈与契約書がない、あるいは形式的
口頭での贈与も法的には有効ですが、税務調査ではその事実を証明することが極めて困難です。贈与契約書を作成していない場合、税務当局からは贈与があったこと自体を疑われる可能性が高まります。
3. 贈与の実態が伴っていない
親の口座から子の口座へ資金が移動したとしても、その後、その資金が親のために使われたり、親の指示で運用されたりしている場合も、贈与の実態がないとみなされます。
1億円の追徴課税を避ける!「税務調査に強い贈与」の秘訣
では、あなたの生前贈与を「無効」にさせず、高額な追徴課税を回避するためには、具体的にどのような対策を講じるべきでしょうか。
1. 贈与の意思と受贈者の認識を明確にする
贈与契約書の作成:最も基本的な対策は、贈与の都度、贈与契約書を必ず作成することです。いつ、誰から誰へ、何を、いくら贈与したのかを明記し、贈与者と受贈者の双方が署名捺印します。
受贈者による管理:贈与された財産(預金など)は、受贈者自身が管理するように徹底します。通帳、印鑑、キャッシュカードなどは受贈者が保有し、親が管理しないようにしましょう。
2. 暦年贈与の基礎控除を最大限に活用する
生前贈与の最も基本的な節税対策は、暦年贈与の基礎控除(年間110万円)を最大限に活用することです。この非課税枠内で毎年贈与を繰り返すことで、贈与税を支払うことなく、長期的に多額の財産を移転することができます。
ただし、毎年同額の贈与を漫然と続けると、税務署から「定期贈与」とみなされ、初年度に一括して贈与されたものとして課税されるリスクがあります。金額を毎年少しずつ変える、贈与のタイミングを変えるなどの工夫も検討すべきです。
3. 相続時精算課税制度を慎重に検討する
2500万円までの贈与が非課税となる「相続時精算課税制度」も、生前対策の選択肢の一つです。この制度は、贈与時には贈与税がかからず、贈与者が亡くなった際に、贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算するというものです。
しかし、一度この制度を選択すると、暦年贈与の基礎控除は適用できなくなるほか、贈与財産を相続財産に加算するため、将来の相続税額が予想以上に高くなる可能性もあります。
贈与だけではない!円満相続と節税のための生前対策
生前贈与は有効な手段ですが、相続税対策は贈与だけに留まりません。
1. 遺言書で「争族」を回避する
遺言書は、単に財産の分け方を指定するだけでなく、家族間の争いを未然に防ぎ、あなたの意思を確実に次世代に伝えるための強力なツールです。遺言書がない場合、「THE争族」と呼ばれる泥沼の争いに発展するケースも存在します。
2. 認知症対策としての任意後見制度の活用
認知症などにより判断能力が低下した場合、資産が凍結され、適切な管理ができなくなるリスクがあります。このような事態に備え、「任意後見制度」の活用を検討することができます。
3. その他の効果的な節税対策
生命保険の活用:生命保険金には非課税枠が設けられており、これを賢く活用することで相続財産を圧縮し、相続税を軽減することができます。
小規模宅地等の特例:特定の要件を満たす居住用または事業用の宅地については、評価額を最大80%減額できる特例があります。
配偶者控除:配偶者が相続する財産には大幅な控除が適用され、相続税がゼロになることも珍しくありません。
複雑な相続手続きも安心!専門家のサポートが不可欠
相続税対策は、法律や税務の専門知識が求められる上に、多岐にわたる手続きが必要となるため、ご自身だけで対応するには限界があります。
相続税に特化した税理士の専門性は、税務調査が心配な方にとって大きな安心材料となります。元国税OBによる税務調査対策により、最小の税金で、かつ税務調査が来にくいように相続税申告を代行することが可能です。
無料で受けられる充実した節税対策も重要なポイントです。初回無料相談では、お客様の状況を詳しくお伺いし、何から始めたらよいかを丁寧にお伝えします。
あなたの資産を守るために、今すぐ一歩を踏み出しましょう
「その贈与、無効です!」と言われ、1億円もの税金を支払う事態は、適切な生前対策と専門家のサポートがあれば、回避できる可能性があります。
しかし、相続税の分野は非常に専門性が高く、刻一刻と変わる税法改正や、税務署の判断基準など、常に最新の情報と深い知識が求められます。素人判断で進めると、かえって多額の税金を支払うことになりかねません。
「相続税はいくらからかかるのか?」といった基礎的な疑問から、複雑な相続トラブルの回避策まで、専門家への相談が重要です。この一歩が、あなたの未来と大切なご家族の笑顔を守る、最も賢明な選択となるでしょう。



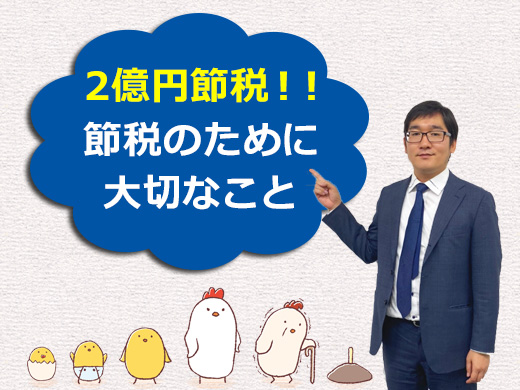

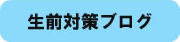
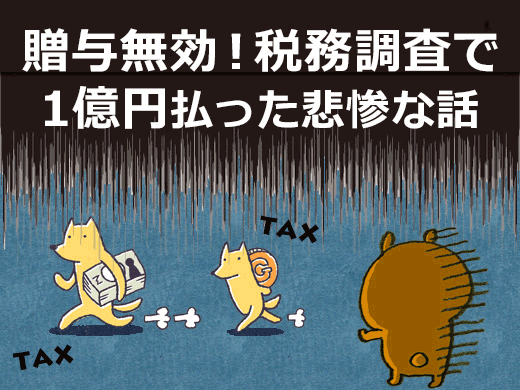

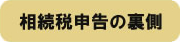


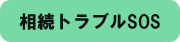
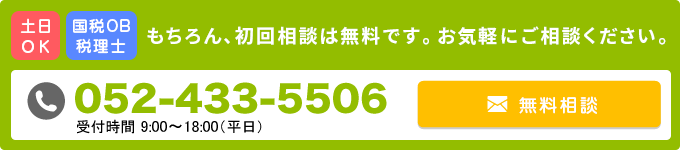
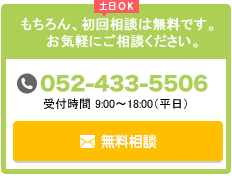

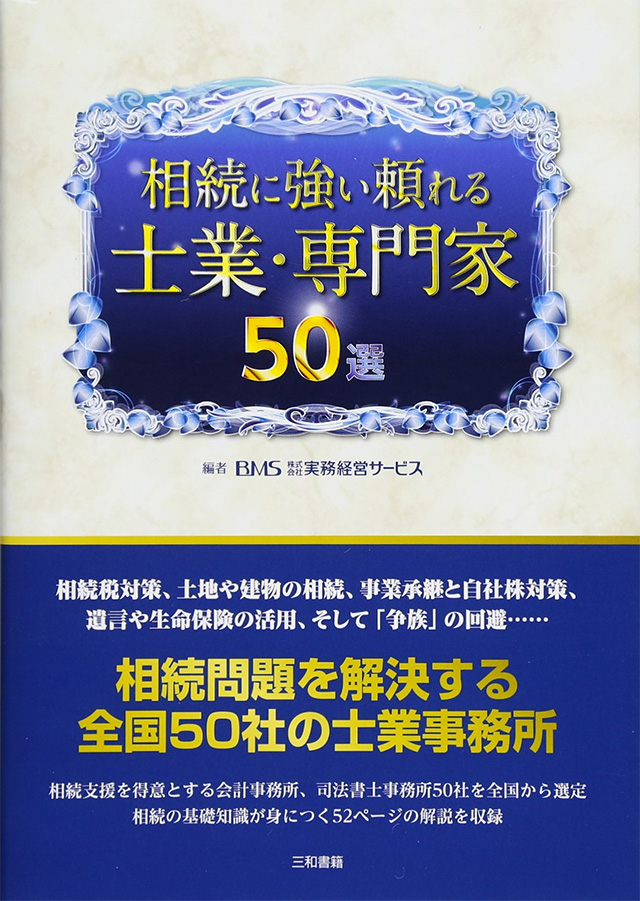
![ダイヤモンド・セレクト 2018年 12 月号 [雑誌]](https://nagae-sozoku.tax/cms/wp-content/themes/nagae-zeiri/img/asin_B07KH1S8NR.jpg)