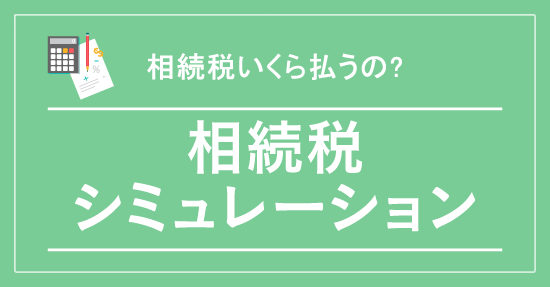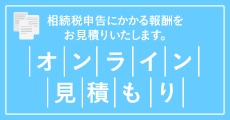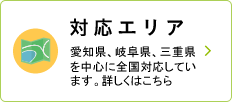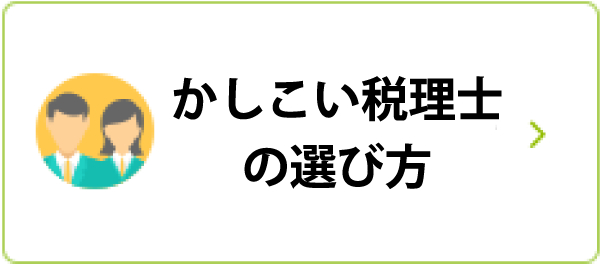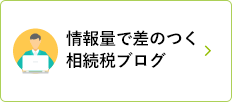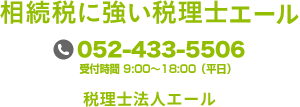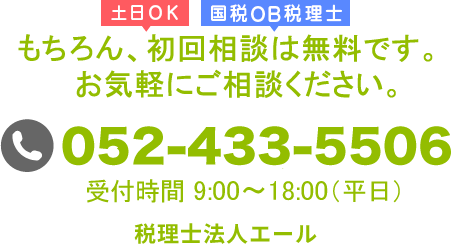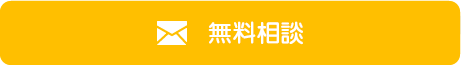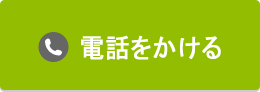グローバル化が進む現代社会において、海外に不動産や金融資産を所有する日本人が急速に増加しています。投資の多様化や国際的なビジネス展開、海外移住など、その理由は様々ですが、こうした海外資産が絡む相続は、国内のみの相続と比較して格段に複雑になることをご存知でしょうか。
適切な対策を講じなければ、想定外の多額の税金負担、複雑な手続きによる時間と労力の浪費、さらには親族間での深刻なトラブルに発展する可能性も否定できません。「残された遺産を1円も無駄にしたくない」、そして「円満相続」を実現するためには、海外資産の特性を深く理解し、早期かつ専門的な対策を講じることが極めて重要となります。
本記事では、海外資産がある場合に特に注意すべき見落としがちなポイントと、その具体的な対策について、実務的な視点から詳しく解説していきます。
目次
相続税申告の専門家によるサポートの重要性
相続税申告の専門家として活動する「相続税に強い税理士エール」の永江将典は、数ある税理士業務の中から相続税申告を専門分野として選択しました。その理由は、相続という人生の重要な節目において、お客様の「1円も無駄にしたくない」という切実な想いを形にすることに、大きなやりがいを感じているからです。
名古屋最安クラスの料金設定、元国税職員による税務調査対策、無料の節税対策提供という3つの柱を軸に、初めての相続で何から始めていいか分からない方でも安心できる手厚いサポートを心がけています。実際、ご相談に来られる方の約80%が初めての相続であることからも、丁寧で分かりやすい説明と適切なアドバイスの重要性を認識しています。
当事務所では、相続税申告、生前対策、相続税還付という3つの主要サービスを通じて、お客様の複雑な相続問題解決を総合的に支援しています。特に、海外資産が絡む相続においては、その専門性と各分野の専門家との連携体制が大きな強みとなっています。
1. 海外資産が絡む相続の複雑性:なぜ「見落としがち」になるのか
海外資産の相続が複雑になる主な理由は、複数の国の法律や税制が複雑に絡み合うためです。国内のみの相続であれば日本の民法や税法を適用すれば済みますが、海外に資産がある場合、その資産が所在する国の相続法や税法、さらには国際的な租税条約まで考慮する必要が生じます。
適用される法律の特定における困難性
まず直面するのが、どの国の相続法が適用されるかを特定することの難しさです。被相続人の国籍、最後の居住地、資産の所在地などによって、適用される法律が異なるため、慎重な検討が必要となります。例えば、日本国籍を持つ被相続人がアメリカに不動産を所有していた場合、その不動産については現地の州法が適用される可能性があります。
財産評価の難しさと専門知識の必要性
海外の不動産や非上場株式など、日本とは異なる評価基準や市場を持つ資産の評価は、非常に専門的な知識を要します。現地の不動産市場の特性、評価慣行、為替レートの適用など、考慮すべき要素は多岐にわたります。
多言語・多文化の障壁による手続きの困難
書類の準備や手続き、現地の専門家とのコミュニケーションなど、言語や文化の違いが手続きをさらに困難にすることがあります。法律用語や税務用語の正確な理解と翻訳は、適切な相続手続きを進める上で不可欠です。
情報の非対称性による判断の誤り
海外の税制や法制度に関する情報は、国内に比べて入手が困難であり、誤った解釈や情報の見落としが生じやすい環境にあります。インターネット上の情報も玉石混交であり、信頼できる情報源の選別が重要となります。
2. 見落としがちなポイントその1:財産評価の特殊性と専門性の重要性
相続税を計算する上で、相続財産の評価額は税額を左右する極めて重要な要素です。特に海外資産の場合、その評価は国内資産以上に専門的な知識と経験を要し、見落とされがちなポイントが多く存在します。
土地評価における多面的な視点の必要性
「相続税還付の鍵は『土地評価』」と言われるように、土地の評価は相続税額に大きな影響を与えます。国内の土地であっても、単純に路線価を適用するだけではなく、土地の形状、利用状況、接道状況、都市計画上の制限など、多面的な視点から見直すことで適正な評価額を導き出すことができます。
海外の不動産についても同様、あるいはそれ以上に専門的な評価が求められます。現地の不動産市場の特性、法規制、評価方法などを深く理解していなければ、過大評価による相続税の払い過ぎ、あるいは過少評価による税務調査のリスクにつながる可能性があります。
金融資産の評価と為替変動リスクへの対応
海外の銀行口座や証券口座にある金融資産の評価も、多くの場合見落としがちです。まず、評価時点の特定が重要であり、相続発生時の為替レートで円換算する必要がありますが、どの時点の為替レートを適用するかが問題となります。
さらに、相続発生から申告・納税までの間に為替レートが大きく変動する可能性があり、その影響を考慮した資金計画が必要です。現地通貨建て資産についても、預金、株式、投資信託など、資産の種類によって評価方法が異なることを理解しておく必要があります。
3. 見落としがちなポイントその2:複数の国の相続税・贈与税制度と二重課税のリスク
海外資産を持つ場合、日本と海外の両方で相続税が課される可能性があります。これを「国際二重課税」と呼び、見落としがちな非常に重要なポイントです。
各国の課税ルールの把握と適用
日本の相続税は、被相続人や相続人の居住地によって課税範囲が異なります。無制限納税義務者の場合、被相続人または相続人のいずれかが日本に住所があれば、日本の国内外にあるすべての相続財産に課税されます。一方、制限納税義務者の場合、被相続人と相続人の両方が日本に住所がなければ、日本国内にある相続財産のみに課税されます。
海外の国も同様に独自の課税ルールを持っています。資産の所在地主義(その国にある資産に課税)や国籍主義(自国民の全世界資産に課税)など、様々な原則があり、これらのルールを理解しないまま手続きを進めると、予期せぬ税負担が発生する可能性があります。
租税条約の活用と外国税額控除の適用
日本は多くの国と「租税条約」を締結しており、これにより国際的な二重課税の排除を目指しています。租税条約の適用がある場合、いずれかの国での課税が免除されたり、外国で支払った相続税を日本の相続税から控除できる「外国税額控除」の制度を活用できる場合があります。
しかし、これらの制度は非常に複雑であり、適用条件も厳格です。条約の有無や内容、控除の計算方法などを正確に理解し、適切に適用しなければ、せっかくの二重課税防止策も無駄になってしまう可能性があります。
生前贈与における国際的なルールの考慮
相続税対策として有効な生前贈与も、海外資産が絡む場合は特別な注意が必要です。日本の贈与税制度には、暦年課税や相続時精算課税制度、教育資金贈与など、さまざまな特例があります。しかし、海外の国でも贈与税(または同様の税金)が課される場合があり、日本の制度だけを考えて贈与を実行すると、二重課税や予期せぬ税負担が生じる可能性があります。
4. 見落としがちなポイントその3:遺言書の作成と遺産分割の難しさ
円満相続を実現するためには、遺言書が非常に重要な役割を果たします。しかし、海外資産がある場合、遺言書の作成やその効力については、見落とされがちなポイントが多く存在します。
遺言書の「有効性」と「適用法」の問題
日本で作成した遺言書が、海外の資産に対して有効であるとは限りません。各国の法律には、遺言書の「形式(書き方)」と「実質(内容の有効性)」に関する規定があり、これらが異なると遺言書が無効と判断される可能性があります。
例えば、日本では自筆証書遺言や公正証書遺言が一般的ですが、海外の国によっては、特定の公証人による認証や複数の証人の立ち会いが必要とされる場合もあります。また、遺言書に記載された内容が、現地の「遺留分(遺産の一部を法定相続人に最低限保障する権利)」などの強行法規に反する場合、その部分が無効となる可能性もあります。
複雑化する遺産分割協議とトラブルのリスク
遺言書がない場合、または遺言書が一部無効とされた場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。海外資産が絡むと、この協議はさらに複雑化します。
海外に居住する相続人がいる場合、連絡や意思確認が難しくなることがあります。また、遺産分割協議の内容を現地で実行するためには、現地の弁護士などの専門家との連携が不可欠です。さらに、相続に対する考え方や慣習が国によって異なるため、協議が難航する場合もあります。
5. 見落としがちなポイントその4:納税資金の確保と納税手続き
相続税の納税は、原則として現金一括払いです。しかし、海外資産の場合、その資産が容易に換金できない性質のものであることが多く、納税資金の確保が見落としがちな大きなポイントとなります。
海外資産の流動性問題への対処
海外の不動産や非上場株式などは、市場が限定的であったり、売却手続きが複雑であったりするため、短期間で現金化することが難しい場合があります。また、為替規制などによって資金の国外送金が制限される可能性もあります。
納税資金が不足した場合、国内資産であれば延納や物納といった制度を利用できます。しかし、海外資産については、これらの制度の適用がさらに複雑になる可能性があります。そのため、生前の段階で、納税資金をどのように確保するか、あるいは海外資産をどう整理するかを計画しておくことが非常に重要です。
申告期限と納税期限の厳守
日本の相続税申告の期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。海外資産の評価や情報収集には時間がかかるため、この期限を見落とすと、加算税や延滞税が課される可能性があります。特に海外資産の申告は時間を要するため、できるだけ早い段階で専門家に相談し、余裕を持った準備を進めることが肝要です。
6. 見落としがちなポイントその5:税務調査への対応と元国税OBの重要性
海外資産を持つ場合、相続税申告の内容は税務署から特に注目されやすい傾向にあります。そのため、税務調査への対応も、見落としがちな重要なポイントです。
海外資産が税務調査で狙われる理由
税務署は、海外に財産が隠されている可能性や、適切な評価がされていない可能性を重視します。金融機関の海外送金情報の把握や、各国との情報交換協定などを通じて、税務署の海外資産に関する調査能力は年々向上しています。
不適切な申告や申告漏れがあった場合、重加算税などの重いペナルティが課される可能性があります。そのため、海外資産に関する情報は、漏れなく正確に申告することが求められます。
元国税OBによる税務調査対策の強み
税務署の内部事情や調査の手法を熟知した元国税OBが申告書作成に関わることで、「税務調査が来にくい」、あるいは「税務調査で慌てない」申告書を作成することが可能になります。これは、海外資産が絡む複雑な相続において特に重要なポイントです。税務署がどのような点に着目し、どのような資料を要求するかを事前に把握し、入念な準備と適切な対応を講じることで、税務調査を円滑に乗り切ることができるでしょう。
海外資産の相続対策は「早めの相談」と「専門家選び」が鍵
海外資産がある場合の相続対策は、国内資産のみの相続とは異なる複雑さと、多くの見落としがちなポイントが存在します。財産評価の特殊性、複数の国の税制、遺言書の有効性、遺産分割の難しさ、納税資金の確保、そして税務調査への対応など、それぞれの段階で専門的な知識と経験が求められます。
これらの見落としがちなポイントを放置すると、相続税額が過大になったり、予期せぬトラブルに発展したりする可能性が十分に考えられます。重要なのは、早期の段階から専門家に相談し、計画的に対策を進めることです。
海外資産の相続対策は複雑ですが、適切な専門家のサポートを受けることで、円満でスムーズな相続を実現することは十分に可能です。早めの専門家への相談が、安心できる相続への第一歩となるでしょう。



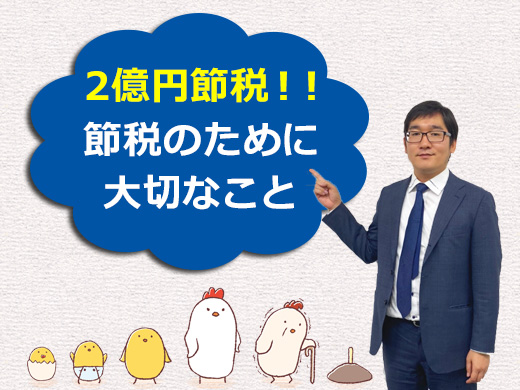

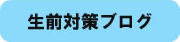
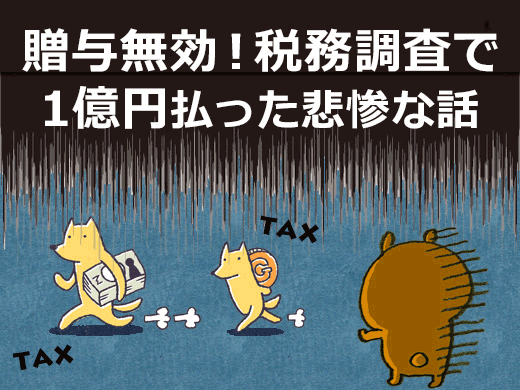

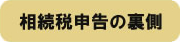


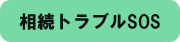
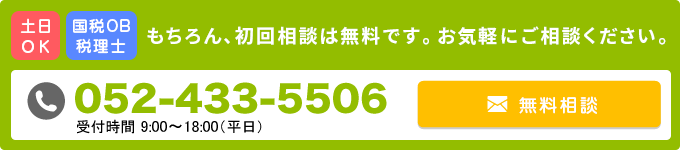
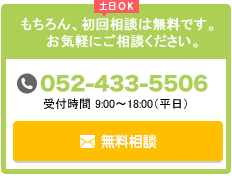

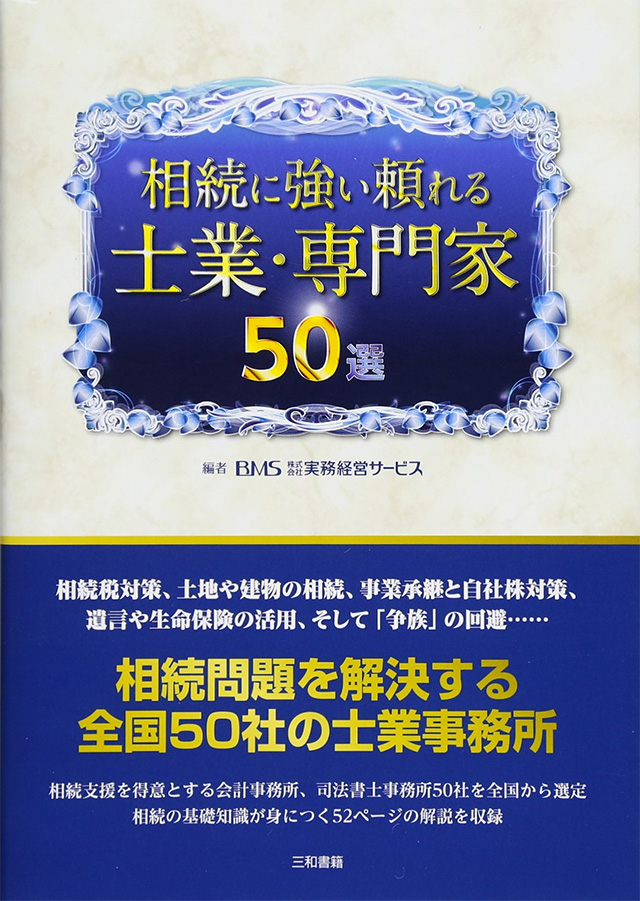
![ダイヤモンド・セレクト 2018年 12 月号 [雑誌]](https://nagae-sozoku.tax/cms/wp-content/themes/nagae-zeiri/img/asin_B07KH1S8NR.jpg)