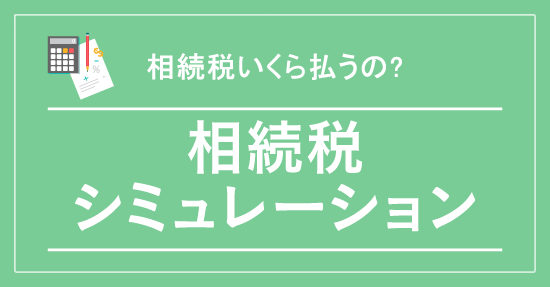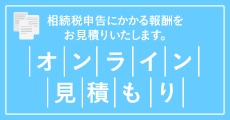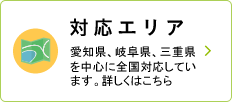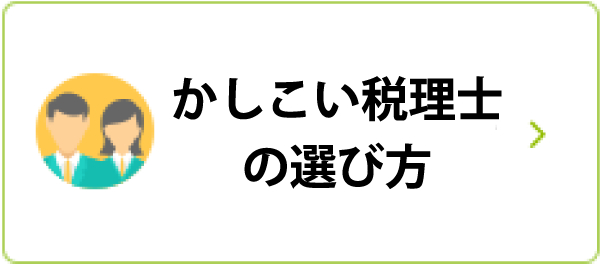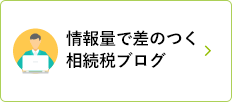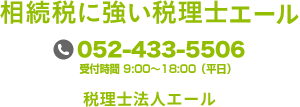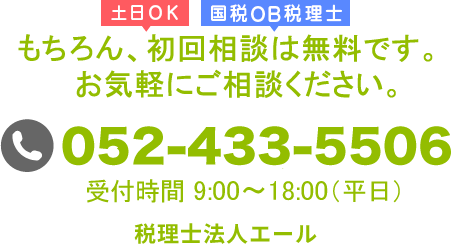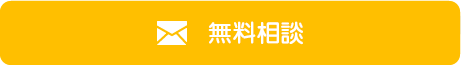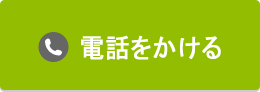目次
遺言書は争族から家族を守る防波堤
相続は、時に残された家族の絆を試す試練となります。故人様が残された財産を巡って、これまで仲の良かった家族が対立し、取り返しのつかない関係の亀裂を生むことは、決して珍しいことではありません。
遺産を巡る深刻な対立は、THE争族と呼ばれる泥沼の事態を引き起こします。信じられないかもしれませんが、実際に遺産分割を巡って「監禁されました」という事件や、遺言書の「捏造」事件が発生し、「財産は全部俺のものだ!」と主張されるケースが存在します。さらには、相続開始後にまさかの「愛人発覚」という衝撃の真実が明らかになることさえあります。
このような相続トラブル(争族)が起こる背景には、故人様の想いが明確に伝わっていないこと、そして相続人同士の利害が複雑に絡み合ってしまうことがあります。特に、相続税の申告が必要なほど資産がある場合、税負担をどう分担するかという金銭的な問題が、感情的な対立を加速させます。財産の多寡に関わらず、相続は家族の絆を試す局面となり得るのです。
相続税で揉める家族、そうならないための最も強力な手段の一つこそ、遺言書を適切に活用することです。遺言書は、親族間の相続トラブルを事前に回避するための重要な生前対策であり、争族にならないための遺産分割のポイントをあらかじめ定めておくことができます。
このブログでは、名古屋を拠点に全国展開する相続税専門の税理士法人エールが、遺言書をどのように活用すれば、家族を争いから守り、かつ税負担を最小限に抑えることができるのか、専門的な視点から詳しく解説します。実務で培った経験と知識に基づいた、実践的なアドバイスをお届けいたします。
1. 遺言書が解決する揉める原因の深層
遺言書がない場合、遺産は法定相続分に基づいて相続人全員の共有財産となり、その分割方法について遺産分割協議を行う必要があります。相続人が一人でも欠けていると協議は成立せず、家族間の意見の対立や感情的なしこりが残っていると、「遺産分割協議が進まない!」という事態に陥りかねません。
遺言書が有効に機能することで、主に以下の「揉める原因」を解消する助けとなります。
1.1. 相続人特定の困難と合意形成の壁
相続人が多数に及ぶ場合、例えば「相続人が500人以上?!」というような超複雑なケースでは、全員の合意を得ることは非常に困難になります。このような事態は稀ではありますが、相続人が数十人規模になることは決して珍しくありません。
相続人が増えれば増えるほど、以下のような問題が発生します。まず、相続人全員を特定し、戸籍を辿り、連絡を取ることが膨大な作業となります。相続人の中には、住所が不明な方、海外に居住している方、高齢で判断能力が低下している方、未成年者など、様々な状況の方が含まれます。
また、相続人同士が一度も会ったことがない、あるいは故人との関係性が非常に薄いというケースも珍しくありません。このような状況で、遺産分割について全員の同意を得ることは極めて困難です。一人でも反対する相続人がいれば、協議は成立しません。
遺言書があれば、遺産の分け方を明確に指定できるため、煩雑な遺産分割協議のプロセスを大幅に簡略化できます。遺言書によって故人様の意思が明確に示されていれば、相続人はその意思を尊重する形で手続きを進めることができます。これにより、長期間にわたる協議や争いを避けることが可能になります。
1.2. 法定相続分と異なる遺産の分割指定
法定相続分は、民法で定められた相続分の目安ですが、必ずしも故人様の意向や家族の実情に合致するとは限りません。
例えば、特定の事業を継いでくれる子どもに多くの財産を継がせたい、あるいは長年連れ添った配偶者に生活の不安がないよう自宅を全て譲りたい、といった故人様の特別な意向がある場合、遺言書はその意向を法的に実現する唯一の手段です。
また、献身的に介護をしてくれた子どもに多めに財産を残したい、逆に、長年音信不通で親の面倒を見なかった子どもには最低限の財産しか渡したくない、といった想いを実現することもできます。さらに、配偶者のいない方が、お世話になった甥や姪に財産を残したい場合や、慈善団体に寄付したい場合なども、遺言書がなければ実現できません。
ただし、遺留分という、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限の取り分があるため、遺言書を作成する際も、この遺留分を考慮し、トラブルにならないための知識を持って作成することが重要です。遺留分を侵害する内容の遺言書を作成すると、相続開始後に遺留分侵害額請求がなされ、結果的に争いの原因となる可能性があります。
遺留分は、配偶者、子ども、直系尊属(父母や祖父母)に認められており、その割合は法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)です。遺言書を作成する際は、この遺留分を考慮しながら、故人様の意思を最大限に実現できる内容にすることが、後々のトラブルを避けるポイントとなります。
1.3. 財産の不透明性やみなし相続財産の盲点
相続発生後、財産目録を作成する際に、名義預金の問題や、みなし相続財産、特に死亡保険金などの扱いを巡って、相続人間に疑念が生じ、トラブルに発展することがあります。
名義預金とは、形式上は配偶者や子ども名義になっているものの、実質的には被相続人の財産とみなされる預金のことです。「この預金は私の名義だから私のものだ」と主張する相続人がいても、実際には被相続人が管理していた場合は、相続財産に含まれます。この判断を巡って、相続人間で争いが生じることがあります。
また、みなし相続財産には、生命保険金、死亡退職金などが含まれます。これらは民法上の相続財産ではありませんが、相続税の計算上は相続財産とみなされます。特に生命保険金の受取人が特定の相続人に指定されている場合、他の相続人から「不公平だ」という不満が出ることがあります。
遺言書を作成するプロセスで、専門家(税理士など)に財産全体を把握してもらうことで、このような税務上の盲点を事前に解消し、財産の内容を明確にすることができます。財産の全体像を把握し、それを相続人に明示することで、「隠し財産があるのではないか」といった疑念を払拭し、透明性の高い相続を実現できます。
2. 遺言書活用と生前対策で円満相続を築く
遺言書を作成することは、単に財産の分け方を決めるだけでなく、「税金を1円でも安く」、そして「親族間の相続トラブルを事前に回避する」という二つの大きな目的を持った生前対策の核心です。
2.1. 遺言書作成と専門家連携
遺言書は、専門家と共同で作成することで、法的な不備や税務上のリスクを避けられます。自己流で作成した遺言書は、形式不備により無効となったり、内容が不明確で逆に争いの原因となったりすることがあります。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自書し、押印する必要があります(財産目録はパソコンで作成可能)。公正証書遺言は、公証人が作成するため、形式不備のリスクがなく、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクもありません。秘密証書遺言は、内容を秘密にしながら存在を証明できる方式ですが、実務上はあまり利用されていません。
弊事務所「相続税に強い税理士エール」(組織変更後は税理士法人エール名北会計、代表社員 石曽根祐司)では、相続税申告だけでなく、遺言書・遺産分割協議書の作成も対応可能です。さらに、初めての相続で何から始めていいか分からない状況であっても、提携している相続に強い弁護士、司法書士、行政書士などの専門家と連携し、すべて弊社が窓口になり打合せを行うワンストップサービスを提供しています。お客様は「依頼する仕事毎にいろんな事務所を探したり、出向く必要はありません」。
税理士は税務面からのアドバイス、司法書士は登記や遺言書の形式面からのアドバイス、弁護士は法律面や争いが予想される場合のアドバイスなど、それぞれの専門分野から総合的にサポートすることで、法的にも税務上も最適な遺言書を作成できます。
2.2. 贈与と遺言書の組み合わせによる節税
遺言書で最終的な意思を確定させつつ、生前に財産を移転する生前贈与は、相続税を減らすための効果的な手段です。
生前贈与には様々な方法があります。暦年贈与では、年間110万円まで非課税で贈与できます。長期間にわたって計画的に贈与を行えば、相続財産を大幅に減らすことができます。また、相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円まで贈与税なしで贈与でき、相続時に精算されます。さらに、教育資金の一括贈与(最大1,500万円)、結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円)といった特例もあります。
しかし、生前贈与にはリスクも伴います。「その贈与、無効です!」として税務調査で1億円を支払う事態になった事例もあるように、税務調査で否認されない税務調査に強い贈与の方法をプロに相談することが肝心です。
贈与が税務上有効と認められるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にすることが重要です。また、受贈者が財産の存在を知り、自由に使える状態にしておく必要があります。通帳や印鑑を贈与者が管理し続けている場合は、名義預金とみなされ、贈与が否認される可能性があります。
生前対策では、「2億円節税」など、あなたの資産を守る具体的な対策も検討できます。財産の規模や家族構成、将来の計画に応じて、最適な生前対策を立案することが重要です。遺言書と生前贈与を組み合わせることで、税負担を最小限に抑えながら、円満な相続を実現できます。
2.3. 認知症対策と財産管理の明確化
親族間の争いは、故人様が判断能力を失った後、財産の管理や使い道が不明確になることから始まることもあります。
認知症になる前に、成年後見制度の活用法を検討しておくことは重要です。成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。法定後見は、既に判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する制度です。一方、任意後見は、判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人を選んでおく制度です。
任意後見制度を利用すれば、信頼できる家族や専門家を後見人に指定し、万が一の際の財産管理や身上監護について、自分の意思を反映させることができます。また、任意後見契約と併せて、生前の財産管理を委任する財産管理委任契約を締結することもできます。
ただし、任意後見制度を「自分でやって大失敗」してしまうケースを避けるためにも、専門家にご相談ください。任意後見契約は公正証書で作成する必要があり、契約内容も法律で定められた要件を満たさなければなりません。また、後見人の選定、報酬の設定、監督人の選任など、慎重に検討すべき事項が多数あります。
生前に財産管理の体制を整えておくことも、将来の争族を避けるための大切なステップです。認知症になってから慌てて対策を講じるのではなく、元気なうちに計画を立て、準備を進めることが重要です。
3. 相続税申告と土地評価が揉め事を激化させる
遺言書で分割方針が示されていても、その財産をどのように評価し、納税するのかという税務上の問題が、次なる揉め事の火種となることがあります。相続税の申告においては、専門性の高いサポートが不可欠です。
3.1. 最小の税金に抑える申告書の作成
弊事務所「相続税に強い税理士エール」は、「残された遺産を1円も無駄にしたくない」という想いを形にするために、相続税申告を選びました。
相続税の申告は、単に財産を計算して税額を算出するだけではありません。様々な特例や控除を適切に適用し、税負担を最小限に抑えることが重要です。例えば、小規模宅地等の特例を適用すれば、自宅の土地の評価額を最大80%減額できます。また、配偶者の税額軽減を適用すれば、配偶者が相続する財産のうち、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか大きい金額まで相続税がかかりません。
これらの特例を適用するためには、様々な要件を満たす必要があり、また、適用の仕方によって税額が大きく変わることもあります。専門家の知識と経験が、大きな差を生むのがこの分野です。
すべての相続税の申告に関する業務を一任していただければ、弊社の方で最小の税金に抑え、かつ、税務調査が来にくいように相続税申告を代行します。税務調査が心配な方、元国税OBが語る相続税申告のツボや、プロの視点、さらには税務調査が来たらどう対応すべきかといった不安も解消できます。
税務調査のリスクを最小限に抑えるためには、申告書の作成段階で、税務署が注目するポイントを押さえ、疑義を招かないよう丁寧に説明資料を添付することが重要です。弊事務所には元国税OBも在籍しており、税務署の視点を理解した上で申告書を作成できることが強みです。
3.2. 土地評価の専門性と還付の可能性
複雑な相続財産の中で、評価額を巡って揉めやすいのが不動産、特に土地や住宅です。相続税還付の鍵は「土地評価」にあります。
土地の評価は、路線価や固定資産税評価額をベースとしますが、実際の評価においては、形状、接道状況、周辺環境、利用状況など、様々な要素を考慮する必要があります。不整形地、がけ地、間口が狭い土地、奥行きが長い土地、騒音や悪臭の影響を受ける土地などは、評価減の対象となります。
路線価だけではない、プロの視点から土地評価を多面的な視点で見直し、適正な評価額を導き出すことで、結果的に相続税額を大きく減らすことができます。もし、過去5年以内に相続税を納税されているなら、払い過ぎた相続税が戻ってくる可能性があり、還付のプロが教えるプロセスを活用することが可能です。還付請求の無料診断も承っています。
相続税の還付請求(更正の請求)は、相続税の申告期限から5年以内であれば可能です。土地の評価を見直した結果、当初の申告より評価額が下がり、納めすぎた税金があれば、還付を受けることができます。弊事務所では、過去の申告内容を精査し、還付の可能性を無料で診断いたします。
相続税を賢く減らす節税ポイントや、非課税財産を活用する方法など、プロの技を駆使して、家族間で税負担の公平性を保ちつつ、総負担を軽減することが、「揉めない」ための重要な要素となります。
相続税の負担が大きくなると、納税資金の確保が問題となり、これが新たな争いの火種となることもあります。生命保険の活用、不動産の売却、物納や延納の検討など、納税資金対策も含めて総合的にプランニングすることが重要です。
4. 専門家を活用するためのアクセスと料金体系
「相続業務は手間がかかる」という理由で受け付けない税理士事務所も多い中で、弊事務所は、初めて相続に直面する方々(ご相談に来られる80%が初めての相続)でも安心して利用できる体制を整えています。
4.1. 圧倒的な利便性とスピード対応
相続税の申告には期限があり、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税する必要があります。手続きを急ぐ必要がある場合も多いです。弊事務所では、必要書類が揃っていれば最短3週間でのスピード申告対応が可能であり、急な相続でも慌てない申告術を提供します。
スピード対応が可能な理由は、効率的な業務フローと、経験豊富なスタッフの連携にあります。相続税申告に必要な書類は多岐にわたりますが、弊事務所では、お客様に分かりやすいチェックリストを提供し、書類収集をサポートします。また、金融機関や役所への照会、財産評価、申告書の作成まで、一貫して迅速に対応いたします。
また、利便性を高めるため、受付時間は平日10時から18時ですが、直通電話090-1294-4160であれば、土日祝日も対応し、夜は22時までご相談をお受けしています。この土日夜間の対応は、お客様からも「土日に対応してもらえ、大変助かりました」と喜びの声をいただいています。
平日は仕事で忙しい方や、遠方にお住まいの方でも、ご都合に合わせてご相談いただけます。また、初回の無料相談はオンラインでも対応可能ですので、全国どこからでもご相談いただけます。
弊事務所は、名古屋税理士会中村支部に所属する税理士法人エール(組織変更後は税理士法人エール名北会計)として、本店を名古屋駅から徒歩3分の立地に構えており、さらに、東京(新宿)、横浜、大阪、そして新設された名古屋北支店と支店を拡大し、全国各地の皆様に質の高い相続業務を提供しています。
名古屋駅から徒歩3分という好立地は、お客様の利便性を第一に考えた結果です。お仕事帰りや用事のついでにお立ち寄りいただくことも可能です。また、全国主要都市に支店を展開することで、地域に密着したサービスを提供しながら、全国のお客様にも対応できる体制を整えています。
4.2. 安価で質の高いサービスと無料相談
弊事務所が選ばれる理由の一つは、名古屋最安クラスの料金でサービスを提供しながらも、質の高いサポートを提供している点です。料金にご納得いただけた場合のみご依頼いただければ問題ありません。
相続税申告の報酬は、一般的に遺産総額に応じて決定されます。弊事務所では、明朗な料金体系を採用しており、ご相談時に概算の報酬額をお伝えいたします。追加料金が発生する場合も、事前にご説明し、ご了承いただいた上で作業を進めますので、安心してご依頼いただけます。
ご相談は、まずは初回の無料相談(最大2時間まで)をご利用ください。相続に関する疑問や不明点にお答えさせていただきます。この無料相談では、無料で節税対策についてもお伝えしています。
初回の無料相談では、お客様の状況をじっくりお伺いし、何から始めたらよいかをお伝えします。相続財産の概要、相続人の構成、既に行っている手続きなどを確認し、今後の進め方を分かりやすくご説明いたします。また、おおよその相続税額の試算や、適用できる特例、節税のポイントなども無料でお伝えします。
また、会計や法人税申告は今の税理士のまま、相続申告のみのご依頼も可能です。既に顧問税理士がいらっしゃる場合でも、相続税の専門性が必要な場合は、弊事務所にご依頼いただけます。顧問税理士との連携もスムーズに行いますので、ご安心ください。
弊事務所には、永江将典(代表社員税理士)をはじめ、相良 信一郎、石塚 直行、阪本 雅人、別所 明子、杉山 祐一といった専門スタッフが在籍しており、相続税専門のプロ集団としてお客様の相続の「困った」を解決し、「争族」を未然に防ぎます。
各スタッフは相続税に関する豊富な知識と経験を持ち、様々な事例に対応してきた実績があります。複雑な案件でも、チーム全体で知恵を出し合い、最適な解決策を見出します。お客様一人ひとりに担当者がつき、責任を持って最後までサポートいたします。
結び:未来の家族のために、今すぐ遺言書を
相続税で揉める家族の悲劇は、適切な準備と故人様の意思表示の欠如から生まれることが少なくありません。遺言書を活用し、生前対策を行うことは、家族への愛がカギとなる相続対策であり、未来の家族を守るための、あなたにできる最善の贈り物です。
相続は、誰にでも必ず訪れる出来事です。しかし、多くの方は「まだ早い」「縁起でもない」と考え、準備を先延ばしにしてしまいます。その結果、突然の相続に直面し、準備不足から家族が争うことになるのです。
遺言書は、あなたの想いを家族に伝える最後のメッセージです。誰にどの財産を残したいのか、なぜそのような分け方にしたのか、家族へどのような想いを伝えたいのか。これらを明確にすることで、家族は安心してあなたの意思を尊重することができます。
また、生前対策を行うことで、相続税の負担を大幅に軽減することも可能です。適切な生前贈与、不動産の組み換え、生命保険の活用など、様々な方法があります。これらの対策は、時間をかけて計画的に実行することで、より大きな効果を発揮します。早めに専門家に相談し、長期的な視点で対策を立てることが重要です。
遺言書作成から相続税の申告、納税まで、相続に関する全ての業務をサポートし、お客様の「1円も無駄にしたくない」という強い想いを実現させることが、私たちの使命です。
名古屋を拠点とする相続税に強い税理士エールは、これまで数多くの相続案件を手がけ、多くのご家族を争族から守ってきました。その経験と実績を活かし、お客様一人ひとりに最適な解決策を提案いたします。
まずは、相続に関するどんな疑問も、初回の無料相談で私たちにご相談ください。遺言書を書くべきかどうか迷っている方、何から始めたらよいか分からない方、既に相続が発生して困っている方、どのような状況でも構いません。お気軽にお問い合わせください。
あなたの大切な家族を争族から守り、円満な相続を実現するために、私たち専門家が全力でサポートいたします。未来の家族のために、今すぐ行動を始めましょう。遺言書という形で、あなたの愛を家族に残してください。



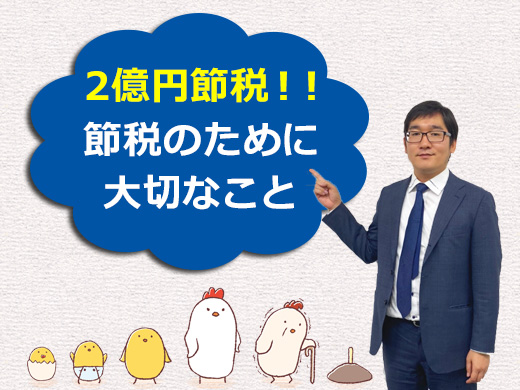

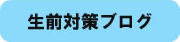
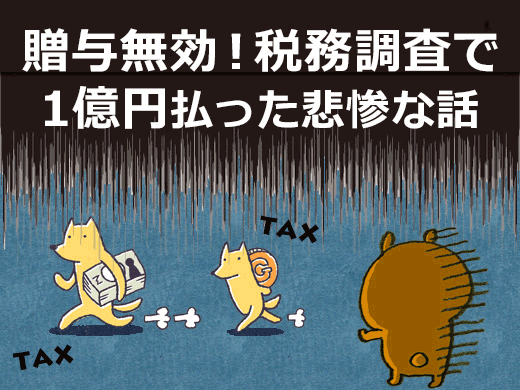

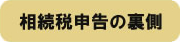


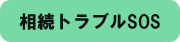
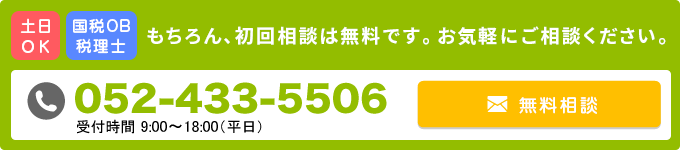
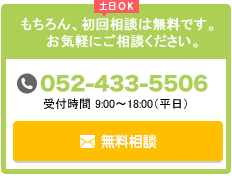

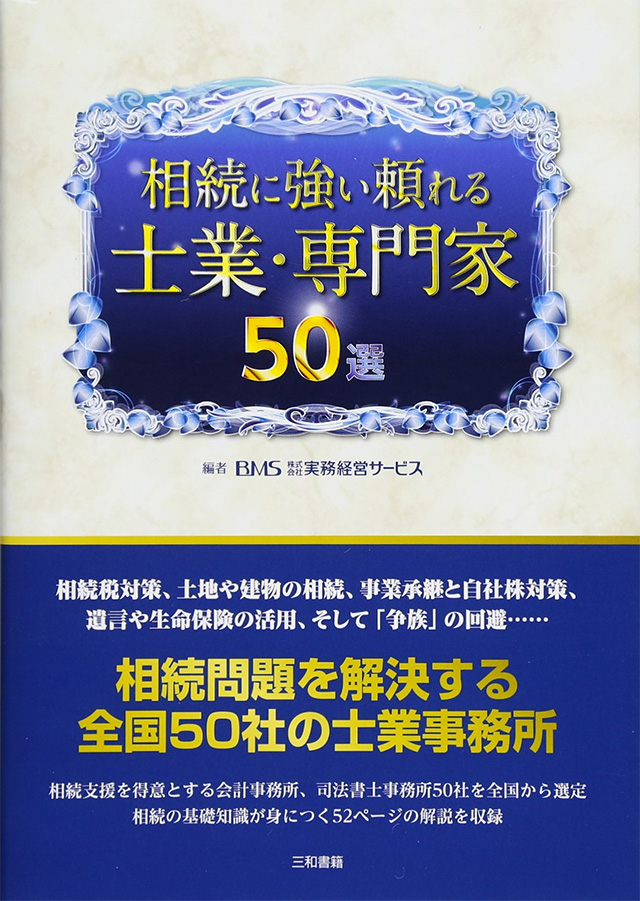
![ダイヤモンド・セレクト 2018年 12 月号 [雑誌]](https://nagae-sozoku.tax/cms/wp-content/themes/nagae-zeiri/img/asin_B07KH1S8NR.jpg)