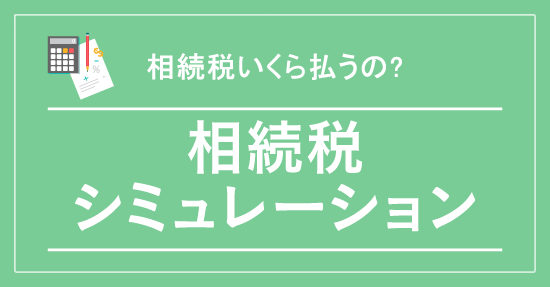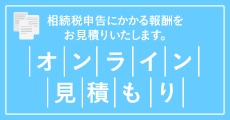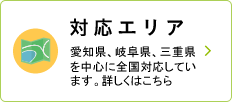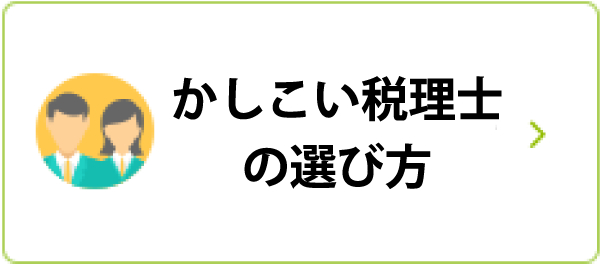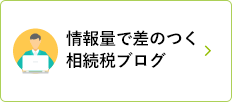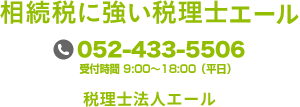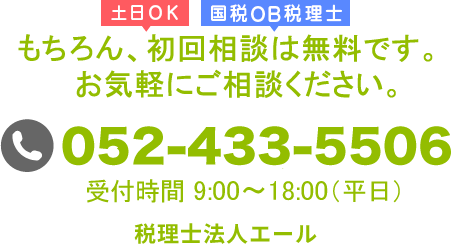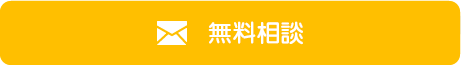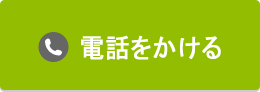目次
みなし相続財産の基本を理解する
相続が発生した際、故人が生前に築いた財産(現金、不動産、株式など)は「本来の相続財産」として相続税の課税対象となります。しかし、税法上、これらの財産とは別に、民法上の相続財産ではないにもかかわらず、相続税の計算においては相続財産と「みなして」課税対象とされる特定の財産が存在します。これが「みなし相続財産」と呼ばれるものです。
私たち税理士法人エールのホームページをご覧になっている多くの方は、相続税申告を依頼する税理士を探しているか、そもそも相続税が発生するか分からないという状況でしょう。ご相談に来られる方の80%が初めての相続であり、財産の仕分けや専門用語の理解に戸惑うのは当然です。
「残された遺産を1円も無駄にしたくない」という皆様の強い想いを実現するためには、みなし相続財産を正確に把握し、適切な非課税枠を適用することが極めて重要です。
本稿では、このみなし相続財産の概念とその取り扱い、そして見落としがちなポイントについて、専門家の視点から詳しく解説します。
みなし相続財産の概念と税務上の重要性
みなし相続財産とは、故人の死亡を原因として取得する財産のうち、民法上の相続によって取得するものではないものの、経済的にみて相続財産と同様の性質を持つため、相続税法上、課税対象とみなされる財産を指します。
なぜ「みなし」相続財産なのか
民法上の相続とは、被相続人の死亡によって、その財産が相続人に承継されることを指します。しかし、被相続人の死亡を原因として取得する財産の中には、厳密には相続によって取得するわけではないものの、実質的には相続財産と同じ経済効果をもたらすものがあります。
これらの財産について課税しないと、相続税の課税の公平性が保てないため、税法上は「相続財産とみなして」課税対象とすることになっています。
典型的なみなし相続財産の種類
みなし相続財産の最も典型的な例は、以下の通りです。
生命保険金(死亡保険金)
故人が保険料を負担し、死亡によって相続人が受け取る生命保険金は、民法上は受取人固有の財産とされますが、相続税の計算においては課税対象となります。
死亡退職金
被相続人の死亡によって、遺族が勤務先から受け取る退職金や功労金も、みなし相続財産として課税対象となります。
生命保険契約に関する権利
被相続人が保険料を負担していた生命保険契約で、まだ保険事故が発生していないものについて、その契約上の権利もみなし相続財産となります。
定期金に関する権利
個人年金保険などで、被相続人の死亡により相続人が年金を受け取る権利を取得した場合、その権利の評価額がみなし相続財産となります。
みなし相続財産と本来の相続財産の違い
みなし相続財産と本来の相続財産には、以下のような重要な違いがあります。
遺産分割の対象となるか
本来の相続財産は遺産分割の対象となりますが、みなし相続財産(特に生命保険金)は受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割の対象になりません。
債務控除の適用
被相続人の債務や葬式費用は、本来の相続財産から控除できますが、みなし相続財産からは控除できません。
相続放棄との関係
相続放棄をした場合、本来の相続財産は取得できませんが、生命保険金などのみなし相続財産は受け取ることができます。
生命保険金の非課税枠を最大限活用する
みなし相続財産の中でも特に重要なのが、生命保険金です。この生命保険金については、相続税を賢く減らすために活用すべき非課税財産としての側面も持っています。
生命保険金の非課税枠の計算方法
生命保険金には相続税の非課税枠があり、以下の算式で計算されます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合、非課税限度額は1,500万円(500万円×3人)となります。
この非課税枠を賢く使うことで、相続税を大幅に減らすことができます。
非課税枠適用の注意点
生命保険金の非課税枠を適用する際には、以下の点に注意が必要です。
相続放棄をした人は非課税枠の適用なし
相続放棄をした人が受け取った生命保険金には、非課税枠の適用がありません。全額が課税対象となります。
法定相続人以外の受取人
受取人が法定相続人以外の場合(例:内縁の妻、孫など)、その人が受け取った生命保険金には非課税枠の適用がありません。
複数の保険金がある場合
複数の生命保険契約がある場合、すべての保険金の合計額に対して非課税枠が適用されます。各保険契約ごとに非課税枠があるわけではありません。
生前対策としての生命保険活用
生命保険は、相続税の節税対策として非常に有効な手段です。生前に保険に加入することで、以下のようなメリットがあります。
納税資金の確保
相続税は原則として現金一括納付が必要です。不動産が多い場合など、納税資金の確保が課題となりますが、生命保険金は死亡後すぐに現金化できるため、納税資金として活用できます。
遺産分割対策
生命保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象外です。特定の相続人に確実に財産を渡したい場合に有効です。
節税効果
非課税枠を活用することで、相続税の課税対象額を減らすことができます。これは合法的な節税対策として、多くの方に活用されています。
みなし相続財産を見落とすことの重大なリスク
みなし相続財産を申告から漏らした場合や、その評価・非課税枠の適用を誤った場合、それは税務調査の格好の的となり、追徴課税という重大なリスクを招きます。
税務調査で狙われやすいポイント
申告内容に不備や漏れがある場合、税務調査が実施されるリスクが高まります。税務署は、故人の過去の口座の動きなどを徹底的に調査し、申告されていない財産の有無を確認します。
みなし相続財産となる生命保険金は、保険会社からの支払情報として税務当局が把握しやすい財産です。そのため、申告漏れがあった場合、税務調査で狙われやすいポイントとなります。
実際に指摘されやすい事例
- 保険契約者と被保険者が異なる契約の取り扱いミス
- 満期保険金と死亡保険金の混同
- 契約者変更があった場合の取り扱いミス
- 非課税枠の計算ミス
- 複数の保険契約の申告漏れ
私たち税理士法人エールでは、元国税職員による税務調査対策を提供しており、最小の税金に、かつ、税務調査が来にくいように相続税申告を代行します。
名義預金との混同リスク
みなし相続財産ではありませんが、故人の財産とみなされるべきで、税務調査でしばしば問題となるものに名義預金があります。これは、故人が家族名義で預金していたものの、実質的な所有権は故人にあったとされる財産です。
みなし相続財産(例:死亡保険金)も名義預金も、一見すると故人名義の財産ではないため、申告漏れが発生しやすいという共通のリスクがあります。
名義預金と判断される基準
- 通帳や印鑑を被相続人が管理していた
- 名義人がその口座の存在を知らなかった
- 名義人が自由に使える状態になかった
- 預金の原資が被相続人の資金であることが明らか
これらの見落としが、税務署からの「お尋ね」が来る原因となり得ます。
生前贈与の失敗リスク
生前に対策として行われる生前贈与も、手続きを誤ると、税務調査で「その贈与、無効です!」と判断され、相続財産に逆戻りして課税されるリスクがあります。
贈与の実態が否認された結果、1億円を支払う羽目になった話のような事例も存在します。
贈与が否認されるケース
- 贈与契約書が作成されていない
- 受贈者が贈与の事実を知らない
- 贈与後も贈与者が資金を管理している
- 贈与税の申告をしていない
みなし相続財産の計算を含め、相続税の節税対策においては、「節税」と「脱税」の境界線、すなわち「グレーゾーン」がどこまで許されるのか、合法的なラインを見極めることが非常に重要です。
死亡退職金もみなし相続財産
生命保険金と同様に重要なみなし相続財産が、死亡退職金です。
死亡退職金の課税関係
被相続人の死亡によって、遺族が勤務先から受け取る退職金や功労金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
死亡退職金にも、生命保険金と同様の非課税枠があります。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
死亡退職金の取り扱いで注意すべき点
支給が確定していない場合
相続開始後3年以内に支給が確定したものが対象です。3年を超えて確定したものは、受け取った人の一時所得として所得税の対象となります。
弔慰金との区別
弔慰金のうち、一定額(業務上の死亡の場合は給与の3年分相当額、それ以外の場合は給与の半年分相当額)までは相続税の課税対象外となります。
複数の勤務先がある場合
複数の勤務先から死亡退職金を受け取る場合、すべての合計額に対して非課税枠が適用されます。
みなし相続財産を含む複雑な相続手続きへの対処
相続税申告は、みなし相続財産だけでなく、不動産の評価や多岐にわたる専門知識を要する複雑な手続きです。これらの手続きを誤ると、特例適用漏れを引き起こすリスクがあります。
土地評価の専門性が鍵となる理由
相続財産において、土地や住宅などの不動産は大きな割合を占めることが多く、その土地評価が相続税額を大きく左右します。
みなし相続財産は主に金融資産が該当しますが、全体の相続税額を最小限に抑えるためには、不動産評価の専門性が不可欠です。
相続税還付の鍵もまた「土地評価」にあり、路線価だけでなく、土地の形状や利用状況などを多面的な視点から見直すことで、適正な評価額を導きます。
私たち税理士法人エールは、税理士、不動産鑑定士、元国税職員が強力にサポートし、専門スタッフが還付の可能性を無料診断しています。過去5年以内に納税した方は、払い過ぎた相続税が戻ってくる還付のチャンスがあります。
専門家連携によるワンストップサービス
相続手続きは、税務申告のほか、以下のような多岐にわたる手続きが必要です。
必要な手続きの例
- 遺言書の検認または作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記
- 預貯金の名義変更
- 株式の名義変更
- 不動産の評価
これらを個別に依頼すると時間と手間がかかり、期限内の申告を妨げる可能性があります。
私たち税理士法人エールでは、相続に強い弁護士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士などと提携しており、すべて弊社が窓口となり、各専門家との打合せや手続きを調整します。
お客様が依頼する仕事ごとにいろんな事務所を探したり、出向く必要はありません。複雑な手続きもワンストップで解決し、申告から納税まで全てをサポートします。
納税資金の確保と争族回避
みなし相続財産を含めた全財産の正確な把握は、納税資金の計画にもつながります。もし納税資金がない場合でも、延納・物納といった選択肢があります。
延納制度
相続税を一括で納付することが困難な場合、最長20年間の分割払いが認められます。
物納制度
金銭での納付が困難な場合、相続財産そのもので納付することができます。
また、財産が複雑に絡み合う相続においては、家族間のトラブル、すなわち「争族」のリスクが常に存在します。
実際に発生したトラブル事例として、以下のようなものがあります。
- 遺産分割で「監禁」された事例
- 遺言書の「捏造」事件
- 愛人発覚といった衝撃的な事例
- 相続人が500人以上いる超複雑なケース
これらのトラブルを事前に回避し、円満相続を実現するためには、遺言書作成などの生前対策が重要です。遺言書作成には多くの注意点があるため、専門家と作成することをおすすめします。
よくあるご質問
Q1. 生命保険金は必ず申告しなければなりませんか?
非課税枠内であっても、相続税の申告書に記載する必要があります。申告書に記載しないと非課税の適用が受けられません。
Q2. 受取人が複数いる場合、非課税枠はどう配分されますか?
各受取人が受け取った保険金の額に応じて、非課税枠が按分されます。
Q3. 契約者と被保険者が異なる場合はどうなりますか?
保険料を実際に負担していた人が誰かによって、課税関係が変わります。複雑なケースは専門家にご相談ください。
Q4. 死亡退職金はいつまでに支給されれば相続税の対象ですか?
相続開始後3年以内に支給が確定したものが対象です。
Q5. みなし相続財産の申告漏れが発覚するとどうなりますか?
過少申告加算税や延滞税が課される可能性があります。悪質な場合は重加算税の対象となることもあります。
専門性の高いサービスとお客様への安心の提供
みなし相続財産のような複雑な概念を含む相続税申告を、名古屋最安クラスの料金で、安価で質の高いサービスとして提供できるのは、相続税申告を専門として選んだ強い想いがあるからです。
無料相談と節税対策の提供
初めての相続で何から始めていいか分からない状況でも、まずは初回の無料相談をご利用ください。状況をお伺いしながら、何から始めたらよいかをお伝えします。
無料相談は最大で2時間まで対応しており、相続に関する疑問や不明点にじっくり向き合います。
また、ご依頼いただいた際の料金は、無料相談の際にお伝えします。料金にご納得いただけた場合のみ、ご依頼いただければ問題ありません。節税対策については、無料で提供しています。
全国対応とアクセスの利便性
専門性の高いサービスを全国の皆様に提供するため、名古屋駅徒歩3分の本店に加え、新宿、横浜、大阪にも支店を拡大し、全国対応を行っています。2021年には名古屋北支店も追加されました。
また、お客様の不安に寄り添うため、直通電話(090-1294-4160)では、土日祝日も夜22時までご相談を受け付けています。急ぎの対応が必要な場合でも、最短3週間のスピード対応が可能です。
元国税職員による徹底サポート
私たち税理士法人エールの強みは、元国税職員による税務調査対策です。税務署の視点を熟知しているため、税務調査が来にくい申告書の作成が可能です。
また、万が一税務調査が入った場合も、元国税職員の経験を活かして適切に対応します。
まとめ:みなし相続財産は専門家の試金石
相続における「みなし相続財産」の適切な取り扱いは、税務上のリスクを避け、最大限の節税を実現するための試金石です。
特に死亡保険金のようなみなし財産や、その適用に関わる非課税枠を正確に理解し、申告に反映させるには、相続税に特化した専門的な知識が欠かせません。
みなし相続財産で押さえるべきポイント
- 生命保険金と死亡退職金が代表的なみなし相続財産
- それぞれ500万円×法定相続人の数の非課税枠がある
- 申告漏れは税務調査の対象となりやすい
- 適切な評価と非課税枠の適用が節税の鍵
- 生前対策としての生命保険の活用が有効
ご自身の財産を正確に把握し、「1円も無駄にしたくない」という想いを実現するため、ぜひ専門家によるサポートをご活用ください。
私たち名古屋の税理士法人エールは、みなし相続財産を含む複雑な相続税申告を、正確かつ迅速に、そして最小の税額で完了させるための専門知識と経験を持っています。
初めての相続で不安な方、相続税がかかるか分からない方、どこから手をつけていいか分からない方、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
土日祝日も夜22時まで相談を受け付けております。電話番号は090-1294-4160です。
皆様の大切な財産を守り、円満な相続を実現するため、私たちが全力でサポートいたします。



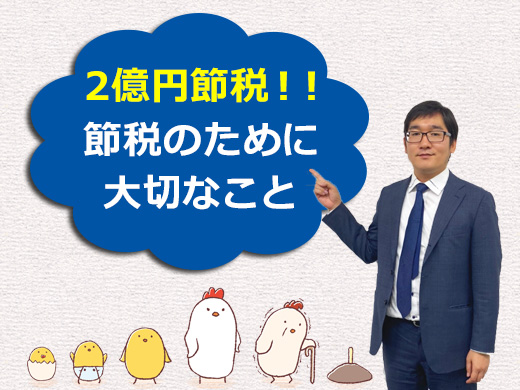

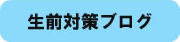
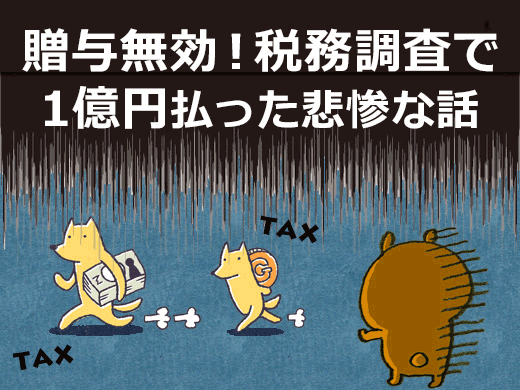

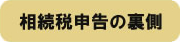


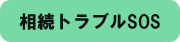
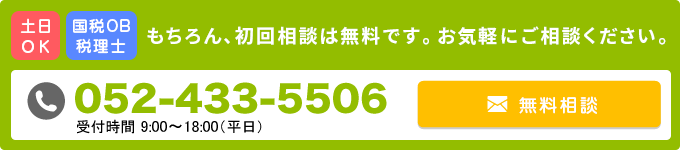
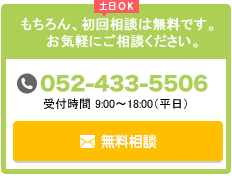

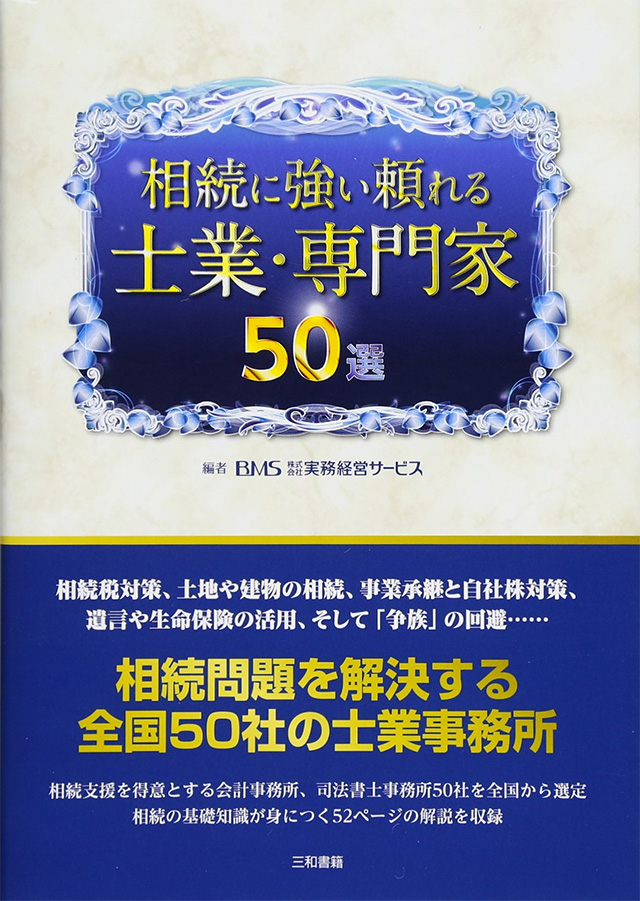
![ダイヤモンド・セレクト 2018年 12 月号 [雑誌]](https://nagae-sozoku.tax/cms/wp-content/themes/nagae-zeiri/img/asin_B07KH1S8NR.jpg)