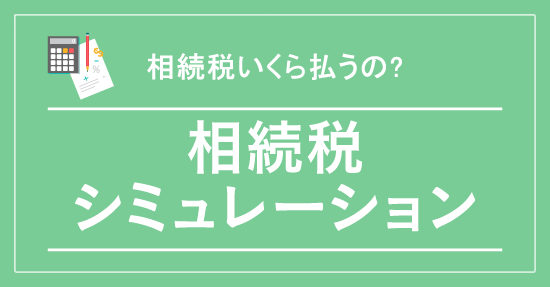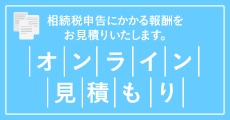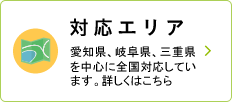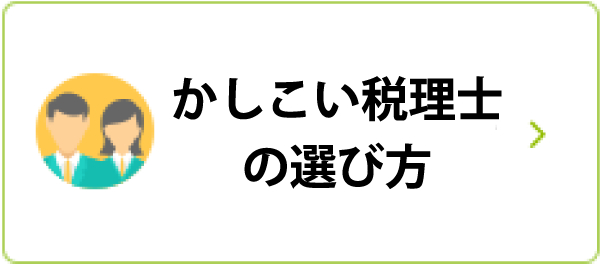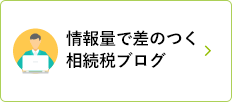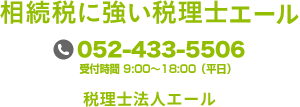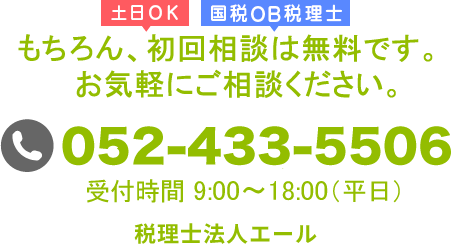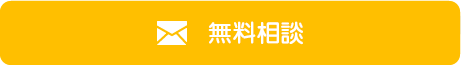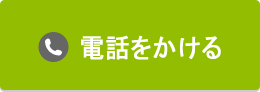遺言書は、生前に自分の意思を記した書面です。15歳以上で意思能力があれば誰でも作成できます。遺言書はどのように作成すればよいのでしょうか。このページでは、遺言書の種類と作成方法、発見した場合の注意点などを解説しています。相続が気になる方は確認しておきましょう。
目次
遺言書は全部で3種類存在する
遺言書には以下の3種類があります。
・自筆証書遺言書
・公正証書遺言書
・秘密証書遺言書
それぞれの概要と作成方法を見ていきましょう。
自筆証書遺言書
自筆証書遺言書は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し捺印する遺言書です。捺印は認印を用いても構いませんが、代筆やパソコンによる作成は認められていません。特徴は、紙とペン、認印さえあれば作成できるのでお手軽な点といえるでしょう。ただし、書き間違えなどにより無効になることが少なくないので注意が必要です。複数作成されたものが見つかった場合は、作成日の新しいものが有効になります。
公正証書遺言書
公正証書遺言書は、法律で定められた手順に沿って公証人などと一緒に作成する遺言書です。具体的には、遺言者が口述などした内容を公証人が筆記し、公証人が読み上げるなどした内容を遺言者と2人以上の証人で確認してから、遺言者・証人・公証人で署名・捺印して作成します。捺印は実印を用いて行います。公正証書遺言書の特徴は、公証人のチェックが入るので不備などで遺言が無効になりにくいことや偽造の恐れがないことです。ただし、2名以上の証人が必要なので手間はかかります。また、公証人に支払う手数料も発生します。作成した公正証書遺言書の原本は役場で管理されます。
秘密証書遺言書
秘密証書遺言書は、遺言者が遺言書に署名・捺印したうえで封印し、公証人と2名以上の証人が署名・捺印などをして作成する遺言書です。秘密証書遺言書は、パソコンや代筆での作成を認められています。捺印は実印でなくても構いません。秘密証書遺言書の特徴は、遺言書の内容を秘密にしたまま本人が作成したと証明できることです。ただし、専門家のチェックを受けられないので、不備により無効になる可能性はあります。また、作成には手数料がかかります。
3種類の遺言書の特徴
3種類の遺言書の特徴をまとめると以下のようになります。
| 遺言書の種類 | 作成方法 | 証人 | 備考 |
| 自筆証書遺言書 | 遺言者が全文・日付・氏名を自書し捺印。 | 不要 | 代筆・パソコンは不可。印鑑は実印でなくてもよい。 |
| 公正証書遺言書 | 遺言者が口述した内容を公証人が筆記。内容を遺言者と証人で確認し署名・捺印。 | 2名以上 | 原本は公証役場で保管。印鑑は実印でなければならない。 |
| 秘密証書遺言書 | 遺言者が遺言書に署名・捺印したうえで封印。公証人と証人が署名・捺印。 | 2名以上 | 代筆・パソコンも可。印鑑は実印でなくてもよい。 |
公正証書遺言以外は開封してはいけない
意図せず遺言書を発見しても勝手に開封してはいけません。なぜ開封してはいけないのでしょうか。
自筆証書遺言書と秘密証書遺言書は検認が必要
自筆証書遺言書と秘密証書遺言書を発見した場合、開封前に検認が必要です。検認とは、家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもと内容を確認するとともに偽造などを防止する手続きのこと(遺言書の効力を認めるものではありません)。自筆証書遺言書と秘密証書遺言書で検認が必要になる理由は、勝手に開封すると他の相続人に偽造などを疑われてしまうからです。検認せずに開封しても遺言書が無効になることはありませんが、5万円の過料を科される恐れがあります。遺言書を発見した場合、家庭裁判所へ提出し検認を受けましょう。
自筆証書遺言書と秘密証書遺言書の開封方法
自筆証書遺言書と秘密証書遺言書は、以下の流れで開封します。
1.被相続人の最後の住所地を管轄していた家庭裁判所へ検認を申し立てる。
2.約1カ月後に、相続人全員に検認の期日が郵送で届く。
3.指定された日に、遺言書と印鑑を持参して家庭裁判所へ行く。
4.家庭裁判所の職員立会いのもと、遺言書を開封する。
5.検認調書が作成される。必要に応じて検認証明書の発行を依頼。
公正証書遺言書は検認の必要なし
公証役場で保管される公正証書遺言書は偽造の可能性が低いため検認を必要としません。他の遺言書に比べ、被相続人の意思をスムーズに反映できる遺言書といえるかもしれません。
3種類の遺言書の特徴を正しく理解しましょう
遺言書には、自筆証書遺言書・公正証書遺言書・秘密証書遺言書の3種類があります。自筆証書遺言は遺言者が全文などを自筆する遺言書、公正証書遺言書は遺言者と公証人、証人が一緒に作る遺言書、秘密証書遺言書は遺言者が作成した遺言書に公証人・証人が署名などをする遺言書です。自筆証書遺言書と秘密証書遺言書は検認が必要なので発見しても勝手に開封することはできません。公証役場で保管される公正証書遺言書は、偽造の可能性が低いため検認を必要としません。それぞれの特徴を理解したうえで作成・開封しましょう。



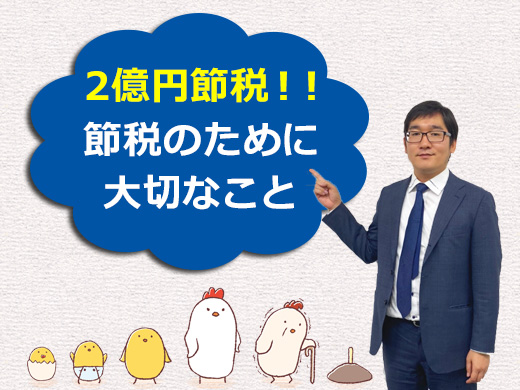

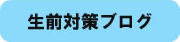
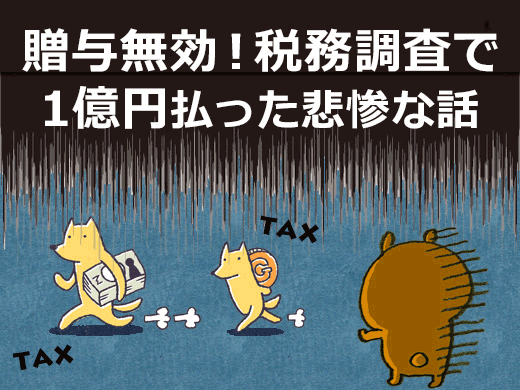

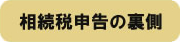


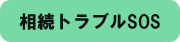
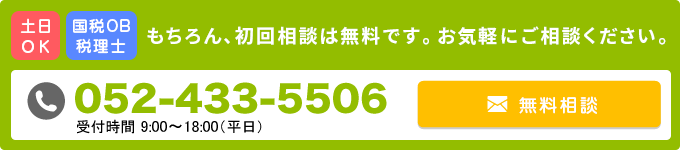
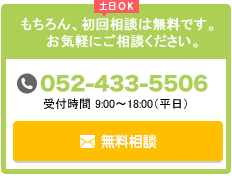

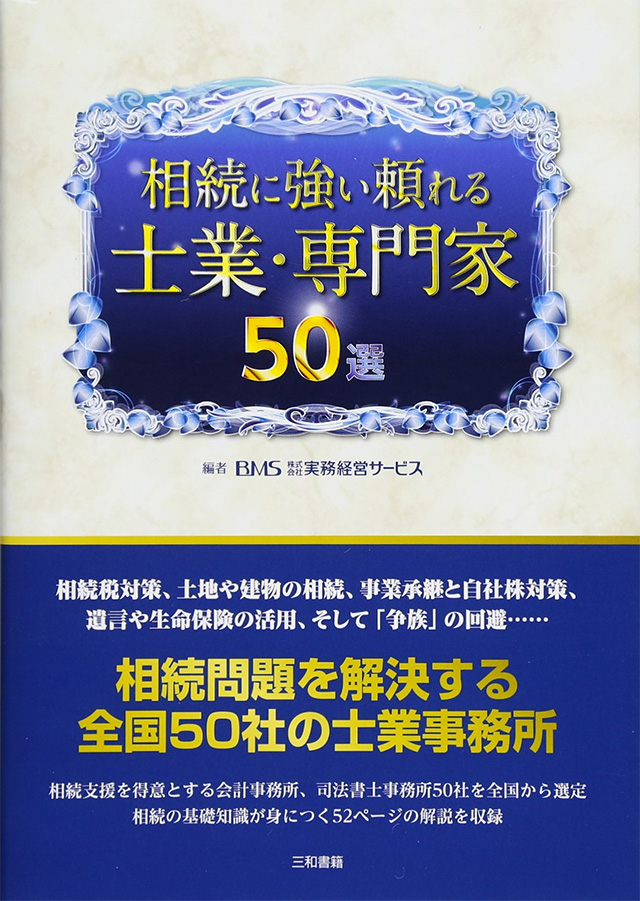
![ダイヤモンド・セレクト 2018年 12 月号 [雑誌]](https://nagae-sozoku.tax/cms/wp-content/themes/nagae-zeiri/img/asin_B07KH1S8NR.jpg)